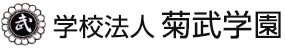令和7年度9月学園研修を開催 教育現場における生成AIの基本を学ぶ
令和7年9月13日、令和7年度9月学園研修が名古屋産業大学文化センター大ホールで開催され、134名の教職員が参加しました。
高木弘恵理事長は、開会の挨拶で、9月1日に防災の日を迎え、改めて必ず発生すると言われている南海トラフ地震への備え・対策について触れ、「地震の予測はできないが、災害による被害は私たちの日ごろの努力によって減らすことができる。家具の固定、非常食や水の備蓄、避難経路の確認、そして、自助・共助を基本とした家族や地域との連携が命や生活を守るための重要なポイントとなる。自分の身の安全を守るために一人ひとりが防災対策に取り組み、日頃からいつ起こるかわからない災害に備えておくことが大切である。この後、東北ボランティア隊が現地での活動や学んだことを発表する。地震への備え・対策、命の大切さについての話をお聞きください」と述べられました。そして、今後の取組として「企業や福祉施設と連携・協働した取組を通じて、実践的な職業教育のさらなる充実を図っていきたい」と述べました。さらに「生成AIは飛躍的な進化を遂げ、社会のあらゆる分野に影響を及ぼす存在となっている。今後はAI技術の普及に向けた取組を進めていくことが重要で、適切に生成AIと向き合い、教育現場で利活用できるよう日々取り組んでいただきたい。本日は、これまでに生成AIを学びたいという要望が教職員から多く寄せられていたため、外部講師をお招きして、生成AIがどのように生まれたのかこれまでの歴史とこれからの生成AIの今後の展望についてご講演をいただく。研修後の翌日から教育現場での実践方法に役立てていただければと思っている」と話されました。
最初に、東北ボランティア隊の活動報告が行われました。今年で4年目となる菊武ビジネス専門学校と菊華高等学校普通科保育・福祉コースの生徒で構成する東北ボランティア隊は「つながりを大切にすること」「積極的に行動すること」を活動目標に掲げ、8月1日から8月4日にかけて、岩手県釜石市と岩手県陸前高田市を訪れて経験した現地での様々な活動を振り返りました。


今年は、岩手県釜石市の旅館「宝来館」の裏山に整備された避難路をさらに安全にするため、野草を刈り、道に張り出した枝を切り落とすなどの作業を行う「宝来館裏山避難路づくりボランティア」に参加して、全員で協力し合い、真剣に取り組むことで、大きな達成感と防災への意識を持つことができました。そして、岩手県立釜石高等学校の有志生徒で構成される「夢団」とのワークショップの中で、語り部メンバーから「災害は止められないが、失われる命を減らすことはできる。そのために家族、友人は避難できていると大切な人の無事を信じる」「自分のことを守れるのは自分しかいない。まずは自分の身を守る」「災害に備えるための準備をすることが大切である」というお話を聞き、震災からの教訓を教わりました。さらに、東日本大震災を後世に伝えるとともに、災害から未来の命を守るための釜石市の震災伝承・防災学習施設「いのちをつなぐ未来館」を訪れ、当時の震災の映像や展示物などを見学し、当時実体した避難路を歩き、改めて震災の恐ろしさを学びました。4日間の様々な体験を通じて、参加した生徒らは「自らが主体となって行動することができるよう普段から心がけていきたい」「日頃から家族や仲間とあらかじめ災害時にどうしておくかを話し合い、避難場所の確認や防災準備をしていきたい」「相手を信頼して願い、家族や友人は絶対避難できていると信じ、まずは自分の身を守ることに心がけていきたい」と力強く語っていました。参加した教職員はそれぞれの生徒の臨場感あふれる堂々とした発表に熱心に聞き入り、すべての報告が終わると大きな拍手が沸きあがっていました。


地域住民の被災体験をもとに防災について共に考え、ふるさと再生にかける私たちの思い、そして、ご支援をいただきました多くの皆様への感謝の気持ちを後世に伝え継いでいくことの大切さを教えていただきました。ありがとうございました。
続いて、教職員が生成AIの活用方法を学ぶために、愛知県が主として中小企業のデジタル人材の育成を支援し、アドバイザーの派遣や社内研修のサポートを行う「愛知県デジタル人材育成支援事業」のサービスを利用し、アドバイザーの久堀駿介氏を講師にお招きして、「教育現場における生成AI活用リテラシー研修 -知る・使う・考える“第一歩”-」をテーマにご講演いただきました。
研修は、①「生成AIで何ができるのかを正しく知る」、②「教職員自身の仕事や生活の中でどう使えるのかを体験する」、③「安全に使うための注意点や考え方を理解する」、④「これからの教育や社会でどう広がっていくのかをイメージする」の4つを目的として、実際にChatGPTに質問して、どんな答えが返ってくるかを体験しながら、ChatGPTや生成AIの利用についてわかりやすく解説していただきました。そして、ChatGPT の精度の回答の質を高めるプロンプトやChatGPT活用に必要な要素について解説され、個人の使いこなし方として、「うまく聞くコツ(プロンプトの基本)」「ロールプレイでの質問の仕方」「ChatGPTと上手に仲良くなる方法」、学校での使い方として、「個人情報や著作権の取り扱い」「使うとき・使わないほうがよいときの判断」「AIに頼りすぎないことの大切さ」について具体的に解説していただきました。さらに、「組織内での活用とデジタル倫理」や「これからの世の中と生成AI」についても解説され、正しい倫理観とルール、情報の正確性やAIエージェントの存在などについて学びました。


参加した教職員は、久堀氏の講演に真剣に耳を傾けていました。講演が終わると、「今回、生成AIの活用リテラシー研修で学んだことを現場に活かしていきたい」と話していました。